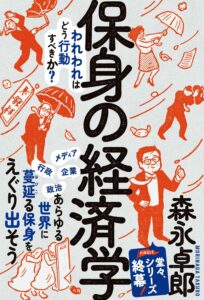
今回は、森永卓郎さん著の『保身の経済学』を紹介していきます!
本書は、これまでベストセラーとなった、『ザイム真理教』や『書いてはいけない』『投資依存症』など、森永卓郎シリーズの最後の1冊となります。
最後の1冊となる本書では、日本経済や私たちの暮らしを壊す、日本社会に蔓延る保身について大胆に書かれています。
この記事では、その本書の中から、森永卓郎が大手メディアから干された理由、なぜ増税派の国会議員が生まれるのか?、値上げ分はどこへ消えたのか?の3つについて紹介していきます!
保身の経済学の要約

森永卓郎が大手メディアから干された理由
森永さんが書かれた『ザイム心理教』は、2025年1月時点で20万部を超えるベストセラーとなりました。
しかし、『ザイム真理教』を刊行して以降、森永さんは、テレビの報道・情報番組のレギュラー出演を全て降板させられてしまったのです。
さらに、日本経済墜落の真相について書かれた『書いてはいけない』は、30万部を超えるほどの大ヒットとなりましたが、出版後、森永さんは情報・報道番組のスポット出演すら失ってしまったのです。
なぜ、森永さんは、『ザイム真理教』や『書いてはいけない』を出版後、大手メディアから干されてしまったのか?
それは、大手メディアで働く社員の保身が理由であると本書で書かれています。
これまで財務省を批判したメディアや評論家は、財務省から制裁を受けているのです。
実際に、財務省の増税路線批判を続けていた朝日新聞には、立て続けに税務調査が入り、重大な課税漏れが指摘されているのです。
そして、執拗な税務調査を受け続けた結果、増税批判を繰り返していた朝日新聞は、増税推進派へと変わってしまったのです。
この財務省からの制裁は、メディアだけでなく、評論家個人も行われています。
森永さんの知人である大学教授は、財務省批判を書いたところ、税務調査で数千万円の追徴金を請求されたそうです。
財務書は税務調査以外にも、スキャンダルの暴露、窃盗、痴漢などの罪を被せて、批判してくるものを社会的に抹殺しようとしてきます。
そのような中で、財務省を痛烈に批判した本を出版した森永さんを、大手メディアは使いたがらないのです。
むしろ使ってしまうと、自分の身や会社に被害をもたらしてしまう可能性があるのです。
そして、大手メディアの社員たちは、40代半ばで年収が1500万円までのぼるなど、高待遇を受けています。
今では、テレビや新聞よりも、ネットの方が勢いがあるのにも関わらず、この大手メディア社員の高待遇は変わっていないのです。
そのため、大手メディアの社員たちは、自分の高待遇を守ったまま定年まで逃げ切ろうとしており、逃げ切るためには、問題を起こさない、組織に逆らわないといったことが重要になります。
だからこそ、大手メディアは、たとえ事実であったとしても、財務省を批判するようなことはしませんし、むしろ事実を捻じ曲げて財務省を擁護するような報道をすることもあるのです。
最近では、きちんとした調査報道を行おうとするメディアがインターネット上で立ち上がっているので、どこから情報をとってくるのかを選別するが大切です。
なぜ増税派の国会議員が生まれるのか?
国民民主党が要求した年収の壁の引き上げは、とても大きな反響を起こしました。
国民民主党が要求した、年収の壁を103万円から178万円へ引き上げることが実現すれば、年収300万円のサラリーマンの場合、年間11万3千円も減税されることになるのです。
しかし、この年収の壁引き上げは、日本維新の会が、自分たちが掲げている教育無償化と引き換えに、補正予算への賛成を与党へ打診したことにより、実現しませんでした。
また、野党第一党である立憲民主党が年収の壁引き上げに賛同してくれていれば、実現も可能だったわけですが、残念ながら立憲民主党は年収の壁引き上げについては静観をしていました。
日本維新の会の共同代表である前原氏と立憲民主党の代表である野田氏は、強烈な増税派として知られています。
実際に2024年の総選挙で日本維新の会は消費税8%へ引き下げを主張していましたし、立憲民主党は2022年までは消費税5%への引き下げを主張していました。
しかし、前原氏と野田氏が代表へ就任したことで、この政策は吹き飛んでしまったのです。
本書では、野田氏は、元は消費税増税に否定的な姿勢をとっていたが、2009年に財務大臣となってから数ヶ月でザイム心理教の布教活動に染まって信者となり、その後総理大臣へとなった時には、消費税10%に引き上げる筋道を作ってしまったと書かれています。
野田氏以外にも、国会議員の中には、元は消費税増税に反対していても、増税派になってしまう人がいます。
では、なぜ増税派の国会議員が生まれてしまうのか?
本書では、それは国会議員の保身が原因であると書かれています。
国会議員へは、年間2000万円以上の歳費が支払われ、無税の調査研究広報滞在費が月額100万円、立法事務費が月額65万円支給されます。
さらに、新幹線のグリーン車に無料で乗れる特別乗車券や秘書を三人まで公費で雇える秘書雇用手当が年間2500万円、民間の家賃相場が60万円の都心マンションを議員宿舎として格安で使用できるという、さまざまな高待遇があるのです。
しかし、これらの高待遇は国会議員としての議席を失ってしまうと、全てなくなってしまいます。
そのため、国会議員が最も恐れていることが議席を失うことなのです。
そんな中、財務省に逆らうことは、とてもリスクのあることなのです。
財務省に逆らうとスキャンダルを暴露されるなど報復を受けて、党からの公認が受けられず、国会議員としての立場を失ってしまう可能性があるのです。
だからこそ、多くの国会議員は、国民生活よりも自分自身の国会議員としての立場を守ることを優先するようになり、増税派へ変わってしまうのです。
もちろん、中には本気で国民の生活を良くしようと尽力してくれている国会議員もいます。
そういった国会議員が1人でも増えるように、やっぱり選挙に行くことは必要なことだと思います。
値上げ分はどこへ消えた?
ここ最近は、物価高、値上げという言葉ばかり聞くようになりました。
商品やサービスが値上げされるのには、インフレや原材料コストの増加など、様々な理由があります。
しかし、欧州では生活費危機とも呼べるほどのインフレが起こっている最中、原材料コストの増加を上回る値上げで企業収益は好調だったのです。
そして、これと似たようなことが日本でも起こっています。
GDPデフレーターという物価指標を見ると、直近からの5四半期でプラス5.5%の上昇を記録しているのです。
このGDPデフレーターには、輸入コストの転嫁で値上げされた分は含まれない指標なので、それを上回る値上げが5.5%だったということであり、その分は企業に収益として入ってきているのです。
では、この5.5%のうち、私たち労働者の給料に反映された分はどれほどあるのか?
その答えは、0.1%です。
残りの5.3%以上は、企業の手元に残っているのです。
皆さんの中にも、物の値段が上がるばかりで、給料が上がらないと感じている人もいるかもしれません。
それは、いくら企業が値上げをしたとしても、企業の利益を増やすだけで、労働者へはほとんど分配されていないからです。
実質賃金は前年比マイナスを続けている一方で、企業の内部留保は増え続け、今では600兆円をこえているのです。
値上げをしても、労働者へは分配されないのであれば、私たちはいったいどうすればいいのか?
本書では、企業が利益拡大を賃金に回さないのであれば、労働者の生活を豊かにする唯一の方法は、企業へ徹底的な値下げを要求することであると書かれています。
そのためには、一円でも安い商品を選択することが大切です。
消費者が一円でも安い商品を選択するようになれば、企業間競争が促進され、私たちの生活が改善されるのです。
また、中には値上げを我慢して、頑張っているところが、まだたくさんあります。
こういった企業やお店の商品を買うことによって、需要を増やしていかないと、値上げを我慢して頑張っている企業はどんどんと倒産していってしまいます。
そうなると、値上げをしている企業の思うツボになってしまい、我々、労働者は賃上げされないのに、値上げされた商品を買い続けることになってしまうのです。
だからこそ、今私たちは徹底的な節約に走ることが大切なのです。
本書では、この記事では紹介しきれていない、今日本社会で蔓延っている、様々な保身について、まだまだ書かれています。
そのため、興味のある方は、ぜひ本書を読んでみてください!
『保身の経済学』の購入はこちらから!
ではでは。