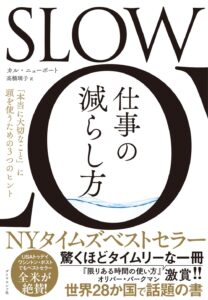
今回は、カル・ニューポート氏の『SLOW 仕事の減らし方』を紹介していきます!
皆さんには、働いても働いても仕事がなくならず、燃え尽きてしまいそう、本当に意味のある仕事に時間を避けていないといった悩みはないでしょうか?
本書はそういった方に役立つ1冊です。
本書は全米で絶賛され、世界28ヵ国で発売されている、今話題の1冊です。
本書では、ジョージタウン大学の准教授を務められている著者によって、知的労働者が燃え尽きることなく、本当に意味のある仕事に集中するための働き方について紹介されています。
この記事では、その本書の中から、若者の間で流行っているひそかな退職、ニセモノの生産性、仕事を減らす方法の3つについて紹介していきます!
SNOW 仕事の減らし方の要約

若者の間で流行っているひそかな退職
新型コロナウイルスが蔓延している最中、アメリカでは、大量離職が相次ぎました。
多くの業種の労働者が、一斉に辞職を出したのです。
辞職を出した理由には、それぞれ色んな理由がありますが、知的労働者の中で共通していたのは、重すぎる仕事の負担を減らしたいというものです。
そして、大量離職の後は、若い人たちの間でひそかな退職が流行りました。
ひそかな退職とは、実際に仕事を辞めるわけではなく、生産性を上げろという要求に応えることをやめて、無駄に頑張らない働き方をすることです。
この動きは、新型コロナウイルスのパンデミックだけによって引き起こされたわけではありません。
パンデミックが起こる前からも、常に仕事過多、ストレス過多な環境で、多くの労働者が働いていました。
そして上司からは、もっと生産性を上げろ、少ない時間でより多くの成果を挙げろとひっきりなしに言われながら働いていました。
以前までは、仕事やストレスの多さに不満を言っても、「みんな頑張っているんだから」「それが仕事ってものだ」と一蹴されていたと思います。
その中で、多くの知的労働者が疲弊し、燃え尽きかけていたのです。
そこに新型コロナのパンデミックが拍車をかけてしまい、多くの労働者が離職やひそかな退職を選ぶようになったのです。
大量離職やひそかな退職はアメリカで話題になったものですが、日本でも、コロナ禍以降、強制的にリモートワークになったことにより、子供がいる環境での仕事に苦労したり、朝夜関係なく、ずっと仕事の通知が来てしまうことに疲れ来てしまったという方も多いのではないでしょうか。
このように、知的労働者の多くが、やってもやっても終わらない仕事、対処しきれないほどのストレスによって、疲弊して、燃え尽きてしまってるのです。
では、なぜ多くの知的労働者は、仕事過多やストレス過多に苦しめられているのか?
続いては、その原因となる、ニセモノの生産性について紹介していきます。
ニセモノの生産性
生産性は、少し前から注目されており、特に日本人は生産性が低いということが話題になりました。
おそらく職場でも、生産性を上げることが重要視されていたり、個人でも生産性を上げるための方法を本や動画から学んでいるという方は、多くいると思います。
ですが、皆さんは生産性とは何なのか?その定義を考えたことはあるでしょうか?
皆さんは、生産性とは何か?と聞かれたら、どのように答えるでしょうか?
「お客様に有益なサービスを多く生み出すこと」
「短い時間で多くのお客様対応をすること」
など、人によって様々な回答が返ってくると思います。
しかし、生産性とは何か?という質問に対する回答は、各々の仕事の内容を答えることが多く、生産性が高いか低いかを判断するための、はっきりとした基準にはなっていないと思います。
多くのサービスや商品を生み出すことや、多くのお客様対応をすることといった回答では、具体的にいくつ作れば生産性が高いとみなされるのかといった基準が曖昧です。
このように、多くの人が考えている生産性には、一貫した定義すらないのです。
そもそも、生産性という言葉が使われ始めたのは、農業分野でした。
農業分野では、土地の単位面積あたりで生み出される作物の量を目安にすることで、生産性を測ることができました。
その後、イギリスで産業革命が起こると、資本家たちは、農業の生産性の考え方を工業に適応し始めたのです。
工業も、農業と同じように、出来上がった成果物の量によって、生産性を測ることができます。
実際に、自動車王と呼ばれたヘンリー・フォードは、ベルトコンベア方式を採用したことで、T型フォードを1台生産する時間を、約12時間半から、1時間半まで縮小させたのです。
このように、農業分野から始まった生産性思考が、そのまま工業にも展開されていき、西欧の経済成長へとつながっていきました。
しかし、そこから20世紀半ばに、工場労働にかわって、知的労働が台頭してくると、話が変わっていきます。
知的労働には、農業や工業で成功を収めた生産性思考が、うまく機能しないのです。
その理由は、作業のわかりにくさにあります。
農業や工業の場合は、どれだけの作物やものを作ることができたかで判断ができました。
しかし知的労働では、いくつもの複雑なタスクを同時に抱えます。
色んな会議に参加しながら、お客様からのメールを返信したり、資料や報告書の作成、新年会の段取りなど、日々多くのタスクをこなしていると思います。
このような、いくつもの複雑なタスクを抱えながら仕事をしている状態では、何を生産性の基準にしていいかわからなくなってしまうのです。
例えば、今年ある人の提案した企画が採用された数が多かったとしても、それは周りが、情報収集や、他の仕事を効率よくこなしてくれていたおかげで、あなたが企画を考えることに集中できていたからかもしれません。
そのような状態では、誰がより生産的なのかを判断することができなくなってしまいます。
さらに知的労働者は、農業や工業労働者のように、全員が同じやり方で働いているわけではありません。
そのため、上司などの管理職は、知的労働者をうまく管理することができていないのです。
このような、生産性の基準が曖昧で、共通のプロセスがないことにより管理の方法に頭の悩ませることになった結果、無理に目に見える活動量を生産性の指標にすることにしたのです。
これを本書では、ニセモノの生産性と呼んでいます。
まさに日本でも、さっさと仕事を終わらせて早く定時で帰る人よりも、残業して長時間オフィスにいる方が上司から「頑張っている」と評価される風潮があっと思います。
それにより、多くの知的労働者は、上司の前でとにかく忙しく働かなくてはいけなくなりました。
さらに、何かしらの成果がすぐに出ない仕事をしていると不安を感じるようになってしまったのです。
その結果、メールや会議など、すぐにできて、上司に仕事をしているアピールができることばかりに首を突っ込むようになり、何かやった気になろうとしてしまうのです。
そして、多くの知的労働者は、仕事そのものよりも、仕事をやっているアピールに費やすことが多くなり、仕事量が増え、燃え尽きてしまうようになったのです。
おそらく皆さんの職場でも、あまり意味のない会議が多くあったり、あまり重要ではない仕事をして、とりあえず仕事をした気分になっているのではないでしょうか?
このような状態では、どんどんと仕事量が増えていってしまい、本当の意味のある仕事に割く時間がなくなってしまうのです。
そこで本書では、持続可能かつ、有意義なやり方で知的労働へ取り組むための働き方として、スローワーキングというものを提唱しています。
スローワーキングには、次の3つの原則があります。
①削減:やるべきことを減らす
②余裕:心地よいペースで働く
③洗練:クオリティにこだわり抜く
『Slow』より
この記事の続きでは、スローワーキングの3つの原則の中から、最も重要であり、まず取り組むべきである、1つ目の削減について紹介していきます!
仕事の減らし方
本当に意味のある仕事に集中するためには、やるべきことを減らす必要があります。
やるべきことを減らすために、まず考えるべきことが、間接コストです。
知的労働者が何か仕事を引き受ける時には、メールやミーティングなど、その仕事を進める上で必要な周辺作業である間接コストが、必ずかかってきます。
そのため、仕事を引き受けるほど、それらにかかる間接コストも増えていってしまい、どんどんと仕事量が膨れ上がってしまうのです。
その結果、いくら労働時間を増やしても、仕事が終わらず、最終的に燃え尽きるようになってしまいます。
だからこそ、余裕があるうちは仕事を増やすというスタンスで働くことをやめるべきです。
そこで、本書ではやるべきことを減らすための方法がいくつか紹介されていますが、この記事では、すぐに実践可能な2つを紹介していきます。
まず一つ目が、仕事の予定時間を全てカレンダーに記入しておくことです。
新しい仕事を引き受けたら、まずはあらかじめ必要な時間を見積もり、仕事の予定時間を全てカレンダーに記入しておきましょう。
仕事の予定時間をカレンダーに記入しておくことで、自分のキャパシティを超えた仕事量を引き受けてしまうことを防ぐことができます。
さらに、仕事を頼まれた際にも、「スケジュールが3週間先まで埋まってしまっています。そのため、今引き受けても、実際に取り掛かるのは1ヶ月後になってしまいます。」と、相手に伝えることが出来ます。
そうすると、仕事を頼んだ側の人は、どうしてもあなたにやって欲しければ、1ヶ月後まで待ってくれるでしょうし、急ぎであれば、他の人に頼むようになります。
仕事を断るのは気が進まないと感じるかもしれませんが、実際に仕事の予定時間をカレンダーに記入しておくことで、スケジュールが埋まっている時は、仕事を断ることが合理的に感じられるようになるのです。
そのため、自分の扱える量以上に仕事を抱えてしまわないようにも、仕事の予定時間をカレンダーに記入しましょう。
続いて、やるべきことを減らす2つ目の方法が、仕事を保留ボックスと実行リストの2つで管理することです。
現在抱えている仕事は、保留ボックスと実行リストの2つに振り分けましょう。
このうち、実行リストに入れるプロジェクトは3つに絞り込みましょう。
ここでいうプロジェクトとは、メールを送るなどの小さなタスクではなく、ホームページを新しくする、会社の忘年会の計画をするなど、大きめの仕事を指しています。
そして、新しいプロジェクを誰かが頼んできたら、とりあえず保留ボックスに投げ込んでおくのです。
もし実行リストにあるプロジェクトが終わったら、保留ボックスから次の仕事をとりに行くのです。
こうすることで、実行中の仕事が少数に絞り込まれるため、大量の仕事に追われる焦燥感から解放される上に、プロジェクトの管理も容易になります。
もしかしたら、中には頼んだ仕事の進捗が遅いと文句を言ってくる人もいるかもしれません。
そういった事態を防ぐためには、新しい仕事を頼んできた時に、自分が今抱えているプロジェクトの数や、完了時期をあらかじめ相手に伝えておきましょう。
そうすることで、相手の期待値とのズレをなくすことができます。
そして、週に一度、実行リストと保留ボックスを見直すようにしましょう。
締切が近いプロジェクトは、より優先して実行リストに入れるようしたり、約束の期日までに終わらなさそうな場合は、依頼主と期日の調整をしましょう。
以上が、今回紹介した仕事の減らし方の方法です。
本書では、仕事の減らし方がまだまだ紹介されておりますので、ぜひ参考にしてみてください!
本書では、この記事では紹介しきれていない、スローワーキングの実践方法がまだまだ解説されています。
そのため、今多くの仕事を抱えすぎていて燃え尽きてしまいそう、本当に意味のある仕事に集中したいと考えている方は、ぜひ本書を読んでみてください!
『SLOW 仕事の減らし方』の購入はこちらから!
ではでは。